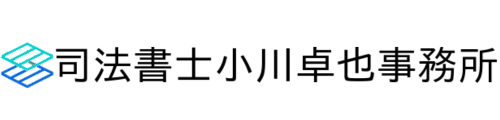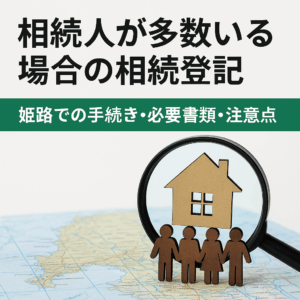相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割の進め方|円滑に進めるための法律知識と実務対応
「家族の一人が認知症になってしまった。そんなとき、相続手続きはどうなるの?」
高齢化社会が進む日本では、このような疑問や不安を抱える方が少なくありません。
特に遺産分割協議では、すべての相続人の合意が必要とされており、認知症によって意思能力が低下した方がいる場合、手続きがスムーズに進まないことがあります。しかし、正しい知識と手続きを踏めば、法的なトラブルを回避し、円満に相続を進めることが可能です。
この記事では、「相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割の進め方」について、司法書士の立場から詳しく解説します。家族の信頼関係を保ちつつ、法律的に正しい対応をしたいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
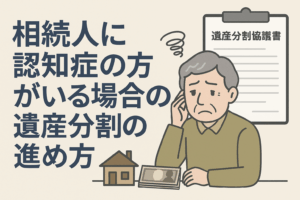
なぜ認知症の相続人がいると遺産分割が進められないのか?
まず大前提として、遺産分割協議はすべての相続人が「法律上の意思表示」をできることが条件です。
つまり、相続人全員が「自分の意思で内容を理解し、判断し、合意する」能力を持っていなければ、遺産分割は成立しません。
認知症と「意思能力」
認知症の方がいても、症状が軽度であれば意思能力を有していると判断される場合もあります。
しかし、進行度によっては意思能力を欠くと見なされることもあり、以下のようなケースが問題になります。
-
内容を十分に理解できない
-
判断能力が著しく低下している
-
他人の影響で意志が左右されてしまう
このような場合、その相続人が行った「同意」は無効とされる可能性が高く、後に相続手続き全体が無効と判断されるリスクがあります。
家族で決めるのはNG?意思能力のない相続人に代わる対応
「母はもう認知症で意思表示なんてできない。でも、家族みんなで相談して決めたから大丈夫だろう」と思ってしまう方もいます。
しかし、たとえ全員が納得していたとしても、法的にはNGです。
意思能力のない相続人の「代わり」に誰かが勝手に協議書に署名することはできません。本人の法的代理人を通じて手続きを進める必要があります。
成年後見制度を活用して代理人を立てる
認知症の相続人が遺産分割に関与できない場合、法的に有効な手続きを行うには成年後見人を選任する必要があります。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人に対して、家庭裁判所が選任した「後見人」が法的な代理を行う制度です。
この制度により、認知症の相続人の権利を守りつつ、他の相続人との協議を適法に進めることが可能となります。
成年後見人の役割
成年後見人は、以下のような法的代理権を持ちます。
-
遺産分割協議に参加し、同意する
-
協議書へ署名・押印する
-
遺産分割の内容が本人(認知症の方)にとって不利益でないかを判断する
重要なのは、成年後見人はあくまで本人の「利益」を優先する立場にあるため、他の相続人と結託して偏った協議内容に同意することはできません。
成年後見人選任の流れ
では実際に、成年後見人を立てるにはどのような手続きが必要なのでしょうか?以下はその流れです。
-
家庭裁判所への申立て
相続人や親族などが、家庭裁判所に対して後見開始の申立てを行います。 -
調査・面談・審査
家庭裁判所が、申立書や医師の診断書を元に、本人の状態を確認します。必要に応じて家庭訪問や面談もあります。 -
後見人の選任決定
申立てからおおよそ2〜3か月ほどで、後見人の選任が決定します。 -
遺産分割協議への参加
選任された成年後見人が、相続人として遺産分割協議に加わります。
成年後見人になれる人とは?
家庭裁判所が成年後見人に選任するのは、以下のような人物です。
-
家族や親族
-
弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職
-
地域包括支援センターや成年後見支援センターなどの第三者機関
ただし、申立てを行った人が希望したとしても、必ずしもその人が選ばれるとは限りません。被後見人の利益を最もよく守れると裁判所が判断する人物が選ばれます。
成年後見制度の注意点とデメリット
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方の権利を守るために設けられた重要な制度です。しかし、すべてのケースにおいて「使いやすい」とは限りません。実際に利用する前に、以下の点を把握しておくことが大切です。
1. 費用と手間がかかる
成年後見制度は申立てから後見人の選任までに2〜3か月かかるほか、申立ての際には医師の診断書や戸籍などの提出が必要です。また、司法書士や弁護士が後見人となる場合には、報酬(年間数万円〜十数万円)が発生することもあります。
さらに、家庭裁判所への報告義務が定期的にあり、預貯金の管理や財産目録の作成といった事務処理も求められることから、家族が後見人になる場合でも想像以上の負担となることがあります。
2. 後見人の自由な判断は制限される
成年後見人は、本人の財産を守る立場であり、遺産分割協議においても本人にとって最も有利な内容でなければ同意できません。
たとえば、相続人全員が「平等に分けるよりも、ある相続人が多く負担してきたから多く受け取ってほしい」と合意していても、それが認知症の方に不利と判断される場合、後見人は同意できないのです。
このため、柔軟な相続協議がしにくくなるという側面もあります。
3. 一度制度を利用すると簡単に終わらせられない
成年後見制度は一時的なものではなく、原則として本人が亡くなるまで継続する制度です。
仮に遺産分割が完了したとしても、後見人としての役割は続き、家庭裁判所への報告義務も残ります。
このことが「制度を使うべきかどうか」の判断を難しくしている背景にもなっています。
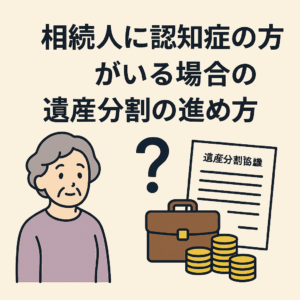
後見人がいる場合の遺産分割協議の進め方と実務ポイント
後見人が選任されれば、遺産分割協議は進めることが可能となりますが、いくつか注意点があります。
【重要】協議内容は「公平性」と「合理性」が必須
成年後見人が遺産分割協議に参加する場合、協議の内容は必ず「本人(被後見人)にとって不利益でないこと」が求められます。
たとえば以下のような分割内容は認められにくい傾向があります。
-
本人に不動産や預貯金をほとんど渡さない
-
他の相続人に一方的に有利な内容になっている
-
本人の生活費や医療費を考慮していない
これらの協議書に後見人が署名したとしても、家庭裁判所の監督下にあるため、無効と判断されることがあります。
複数の認知症相続人がいる場合の対応は?
一層注意が必要なのは、相続人の中に認知症の方が複数いるケースです。たとえば、兄弟姉妹全員が高齢で、2人以上が意思能力を欠いているというようなケースでは、それぞれに成年後見人を選任しなければなりません。
負担と時間が倍増する
成年後見人の選任には、通常1人あたり1件の申立てが必要です。つまり、2人分であれば書類も2セット、診断書も2通、申立費用も2倍です。
また、それぞれの後見人が別々の専門家になる場合、遺産分割協議をまとめるまでに時間がかかる上、協議が複雑化するリスクもあります。
よくある質問とその回答(FAQ)
Q1. 認知症の父の代わりに、私(子ども)が遺産分割協議書に署名してもよい?
A. いいえ、できません。
本人に意思能力がない場合、たとえ子どもであっても「代理人」としての法的権限がなければ無効です。成年後見人などの法的代理が必要です。
Q2. 認知症の兄が遺産分割で不利になっても、家族が納得していれば問題ない?
A. 原則として無効となる可能性が高いです。
遺産分割協議は「全員の自由意思に基づく合意」が必要です。不利益な内容は後に争いの原因となり、家庭裁判所で争われることがあります。
Q3. 成年後見制度を使うと、自宅を売却したりできなくなるの?
A. 基本的にはできますが、家庭裁判所の許可が必要です。
後見制度は「保存行為」が原則ですが、自宅売却などの重要な財産処分には家庭裁判所の許可が必要です。家族信託の方が柔軟に対応できるケースもあります。
【相続事例紹介】認知症の相続人がいた遺産分割の実例
現実には、「認知症の家族が相続人に含まれている場合、どう進めたらよいのか?」という疑問を抱く方が非常に多いです。ここでは、実際に司法書士が関わった事例を通して、より具体的な流れとポイントを見ていきましょう。
事例1:母親が重度の認知症、兄弟3人での遺産分割
状況:
姫路市に住むAさんは、父親の死後、母親と兄・妹の3人で相続人となりました。
しかし母親はすでに認知症が進行しており、施設に入所中。日常の会話も難しく、遺産分割の協議に加われる状態ではありませんでした。
対応:
司法書士の助言を受け、家庭裁判所に成年後見人の申立てを行い、弁護士が後見人に選任されました。
その後、母親の法的代理人として後見人が遺産分割協議に参加し、母親にとって不利益にならないよう、公平な配分で合意が成立。
結果:
登記や預貯金の手続きも滞りなく完了し、兄弟間での争いもなく、スムーズな相続が実現しました。
ポイント:
-
家族が納得していても、後見人が就任しなければ手続きは無効になりうる
-
成年後見制度を使うことで、後のトラブル防止につながる
事例2:兄と弟の2人相続、認知症の兄の意思が確認できず協議が難航
状況:
Bさん(弟)は、認知症の兄と2人きりの兄弟で、両親の遺産を相続することに。
兄は長年施設に入っており、明確な意思表示は不可。Bさんとしては兄の面倒を見てきたので自宅の土地建物を譲ってもらいたいという考えでした。
対応:
当初は家族間での話し合いで済ませようとしましたが、司法書士に相談したところ、「意思能力のない相続人を無視して進めるのは違法」との説明を受け、後見人の選任を実施。
結果:
後見人からは「不動産のすべてを弟に譲るのは、兄に不利益」と判断され、裁判所を通じて、兄にも金銭で相応の財産を分配する形で最終的に合意に至りました。
ポイント:
-
長年介護をしていたことと相続割合は別問題
-
認知症の方の権利を守る視点が不可欠
相続トラブルを避けるために今からできる3つのこと
認知症が関係する相続は、想像以上に手続きが煩雑で、心理的・金銭的な負担も大きくなりがちです。
ここでは、将来に備えて今すぐできる3つのポイントを紹介します。
1. 家族間で早めに話し合いを持つ
「相続の話は縁起でもない」と考える方も多いですが、現実的には元気なうちに話し合っておくことが家族のためです。
-
どの財産を誰が引き継ぐか
-
認知症になった場合どうするか
-
成年後見制度や家族信託を利用する意向があるか
こうした点を事前に共有するだけでも、将来の混乱を大きく回避できます。
2. 遺言書を作成しておく
遺産分割でもめるケースの多くは、「故人の意思が不明確なまま相続が始まる」ことに起因しています。
そこでおすすめなのが、公正証書による遺言書の作成です。
特に以下のような方は遺言書の作成を検討しましょう。
-
相続人に認知症や障害を持つ人がいる
-
兄弟姉妹間の関係があまり良好ではない
-
特定の相続人に多く遺したい意向がある
公証人が関与する公正証書遺言であれば、形式不備で無効になるリスクも少なく、法的にも強い効力があります。
3. 信頼できる専門家に定期的に相談する
相続や認知症に関わる制度は年々変化しています。
自分だけでネット情報を集めて判断しようとすると、かえって間違った方向に進んでしまうこともあります。
特に以下のような場面では、地域に強い司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、大きな安心が得られます。
-
親や配偶者が認知症の診断を受けた
-
遺産分割を始めたいが、意思表示ができない人がいる
-
成年後見の申立てや書類の作成が難しい
-
相続人の中に連絡が取れない人がいる
家族の「幸せな相続」を実現するために大切なこと
認知症を患った家族の存在は、誰にとっても心の負担になります。
それが相続というデリケートな場面であればなおさら、感情的な対立や誤解が起きやすくなります。
しかし、法的な手続きをしっかりと踏み、「誰の権利も損なわず、家族全員が納得できる相続」を目指すことで、家族の関係を壊さず、むしろ深めることすら可能です。
相続とは、単なるお金や不動産の分配ではありません。
それは、親の思い出、家族の歴史、そして信頼関係の整理でもあるのです。
地元の司法書士に依頼するメリット
-
地元の家庭裁判所や法務局の運用に精通している
-
ご高齢の相談者にも丁寧な説明を心がけている事務所が多い
-
自宅や施設への出張相談に対応している場合もある
-
地域の金融機関・税理士・行政との連携もスムーズ
特に、認知症を伴う相続の相談は専門性が高く、個別対応が必要なため、地域に根差した専門家を味方につけることで、心強く安心して手続きを進めることができます。
最後に|あなたの相続、安心して任せられる人はいますか?
家族の大切な財産を巡る相続において、認知症という現実は避けて通れません。
しかし、法的な知識と信頼できる専門家の力を借りれば、円滑で公平な遺産分割は実現できます。
「まだ先の話」と思っていても、ある日突然、相続は始まります。
そのときに慌てないためにも、今のうちから情報を集め、備えることが大切です。
もし、少しでも不安や疑問を感じたら、一度司法書士に相談してみてください。
あなたと、あなたの大切な家族の未来を守る第一歩になるはずです。