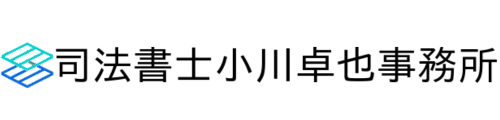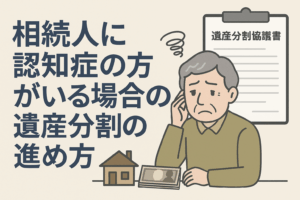姫路で賃貸物件を相続したら?相続登記の義務化・手続き・費用・注意点を解説
「親から賃貸物件を相続したけれど、何から始めればいいのかわからない」
「姫路で不動産を受け継いだが、入居者との契約や管理はどうなるのか心配」
「固定資産税や修繕費、将来の負担を考えると不安」
こうした声は、賃貸物件を含む不動産を相続した方からよく聞かれます。特に2024年4月から相続登記が義務化され、放置していると10万円以下の過料を科されるリスクがあるため、早めの対応が欠かせません。さらに、相続財産が賃貸中の物件の場合は、入居者との契約継続や家賃収入の管理、修繕対応なども同時に引き継がれるため、通常の相続よりも複雑になりがちです。
この記事では、最新制度に沿った手続きの流れ、必要書類、費用の目安、相続人が多い場合の注意点をわかりやすく解説します。

相続と賃貸物件に関する基礎知識
相続登記義務化のポイント(2024年4月施行)
-
3年以内に登記が必須
被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。 -
賃貸物件も対象
マンションやアパートなど、入居者が住んでいる賃貸物件も例外ではなく、相続登記を行う必要があります。 -
2027年3月31日が目安
2024年4月より前に発生した相続については、原則として2027年3月31日までに登記を済ませなければなりません。
👉 ポイント
相続登記は「不動産を誰の名義にするか」を法的に確定させる重要な手続きであり、賃貸物件でも同じルールが適用されます。
賃貸借契約は相続後どうなる?
不動産の所有者が亡くなっても、入居者との賃貸借契約はそのまま有効です。
-
家賃は相続人に引き継がれる
-
建物の修繕義務も相続人が負う
-
敷金返還義務も引き継がれる
つまり、相続によって「大家(貸主)」の立場が新しい相続人に移る形になります。入居者が突然住めなくなる心配はなく、家賃の支払い先を変更するだけで契約は続行されます。
相続人が多数いる場合に起きやすい問題
相続人が複数いる場合、以下のようなトラブルが起きやすくなります。
-
誰が家賃を受け取るかで意見が分かれる
-
修繕や建物管理の判断に全員の同意が必要になり、意思決定が遅れる
-
入居者への対応が不十分になり、信頼を損ねる
このような事態を避けるため、代表相続人を定めて管理を一元化することが実務上は重要です。
姫路で賃貸物件を相続したときの手続きの流れ
1. 不動産の確認と相続人の確定
まずは対象不動産と相続人を明確にします。
-
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得
-
姫路市役所で名寄帳(固定資産課税台帳)を入手
-
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して、相続人を確定
2. 法定相続情報一覧図を活用
法務局に戸籍一式を提出して法定相続情報一覧図の写しを作成すると、銀行や税務署、不動産の各種手続きで繰り返し使えます。相続人が多い場合や書類の提出先が多い場合などでは書類のやり取りを効率化できるため有用です。
3. 遺産分割協議
賃貸物件を誰が相続するかを相続人全員で話し合います。
-
単独相続+代償金の支払い(1人が物件を相続し、他の相続人へ金銭で調整)
-
共有相続(複数人で相続する。ただし将来の管理で不便)
将来的なトラブルを防ぐためには、共有ではなく単独相続が望ましいケースが多いです。
4. 相続登記の申請
姫路市、神崎郡(神河町、市川町、福崎町)の不動産の管轄法務局は、神戸地方法務局姫路支局です。
必要書類をそろえて、神戸地方法務局 姫路支局へ申請します。
5. 賃貸借契約の引き継ぎ
相続登記後は、入居者に所有者が変わったことを通知します。
-
家賃振込先の変更
-
修繕や契約更新の対応
-
敷金や退去精算の引き継ぎ
これらをスムーズに行うには、不動産管理会社を通じて連絡するのが安心です。
賃貸物件の相続で注意すべきこと
相続人が多数いるとき
-
家賃収入や修繕費の分配でトラブルになりやすい
-
代表相続人を定めると管理がスムーズ
空室や老朽化物件の場合
-
修繕費がかさみ、収支がマイナスになるリスク
-
老朽化が進めば建て替えや取り壊しを検討する必要
税金面の負担
-
固定資産税
-
相続税(基礎控除を超える場合)
-
将来売却時の譲渡所得税
相続と賃貸物件にかかる費用・司法書士に相談するメリット
相続と賃貸物件にかかる費用の目安
登録免許税(法務局に納める税金)
相続による不動産の名義変更には「登録免許税」がかかります。計算方法は次のとおりです。
-
固定資産税評価額 × 0.4%
たとえば、姫路市内の賃貸マンションの固定資産税評価額が3,000万円の場合、
→ 3,000万円 × 0.4% = 12万円 が必要です。
※評価額は、毎年、姫路市役所から通知される「固定資産課税明細書」等で確認できます。
書類取得のための実費
相続登記に必要な書類を集める際には、次のような費用がかかります。
-
戸籍謄本:1通450円
-
除籍謄本・改製原戸籍:1通750円
-
住民票除票・戸籍の附票:1通300円前後
-
名寄帳(姫路市役所で取得可能):1通300円程度
-
登記事項証明書:1通600円(オンライン請求:1通520円または490円)
👉 相続人が多い場合、本籍地が複数の自治体に分かれていることも多く、数万円単位の実費になるケースも珍しくありません。
司法書士に依頼する費用(報酬)
司法書士へ依頼する際の費用は、事務所や案件の複雑さによって異なりますが、目安は以下のとおりです。
-
基本的な相続登記手続き:7万〜15万円程度
-
戸籍収集・相続関係説明図作成も含む場合:10万〜20万円程度
-
相続人が多数いたり、海外在住者が含まれるなど複雑な場合はさらに増える可能性あり
👉 費用は「不動産の数」「相続人の人数」「作業の範囲」に応じて変動するため、事前に見積もりを取ることが安心につながります。
賃貸物件を相続する際のリスクと注意点
家賃収入をめぐるトラブル
相続人が複数いると、家賃収入の分配をめぐって意見が食い違いやすくなります。代表相続人を定めて家賃管理を一元化しないと、入居者に二重請求してしまうなどのトラブルにつながるおそれがあります。
老朽化・空室リスク
古い賃貸物件を相続した場合、修繕費が増えたり空室が続いたりすることで、収支が赤字に転じる可能性があります。相続人同士で「維持するか、売却するか」を早めに話し合っておくことが重要です。
共有登記のデメリット
相続人全員で共有名義にすると、
-
売却
-
修繕
-
担保設定(ローンを組む場合)
すべてに全員の同意が必要になります。人数が多いほど意思決定が難航し、物件の活用が制限されるため、単独相続+代償金支払いなどで整理するのが望ましいケースが多いです。
司法書士に相談するメリット
戸籍収集と相続人確定をスムーズに
相続登記には「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を揃える必要があります。複数の市区町村にまたがると非常に煩雑ですが、司法書士に依頼すれば迅速かつ正確に収集してもらえます。
相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
司法書士は、相続人の関係を整理した「相続関係説明図」や、ご要望があれば法務局の認証を受ける「法定相続情報一覧図」を作成します。これにより、金融機関や税務署での手続きが大幅に簡略化されます。
遺産分割協議の実務アドバイス
司法書士は代理交渉はできませんが、実務上「賃貸物件を誰が相続するか」「収益性を考えるとどんな分割が合理的か」といった相続人同士の合意形成のお役に立てるようアドバイスをしてくれます。相続税の申告など税務上の問題が関係する場合は、税理士さんに関与してもらうことになるかと思います。
例1:賃貸物件を単独で相続するケース
姫路市内にある賃貸マンションを相続する際、相続人が複数いると「共有にするか」「誰か1人が相続するか」で意見が分かれることがよくあります。
-
共有にすると修繕や売却などの手続きに全員の同意が必要となり、将来のトラブルの火種になりやすい
-
実務的には、1人が物件を相続し、その人が他の相続人に代償金(お金での補償)を支払う方法がスムーズ
👉 将来のリスクを具体的に示し、数字で比較できる資料を提示することで、話し合いがまとまりやすくなります。
例2:代償金をすぐに用意できない場合
相続財産の多くが不動産で、現金が不足していると「代償金をどう支払うか」が大きな課題になります。
-
不動産の一部を売却して資金を確保する
-
銀行の融資を利用して、長期で代償金を分割払いする
-
賃貸収入を一定期間、他の相続人に分配する方法を検討する
👉 「現金がないから分けられない」という思考を避け、柔軟な解決策を選べるようになります。
例3:老朽化した賃貸物件の扱い
築年数が古く、修繕費がかさみそうな賃貸物件は、単純に相続して持ち続けるよりも、売却や制度の活用を検討したほうが良いケースがあります。
-
修繕費や固定資産税などの維持コストを試算する
-
家賃収入とのバランスを見て「持ち続けるか、売却するか」を判断
👉 感覚ではなく数字で判断できるため、相続人同士が冷静に話し合えるようになります。
期限内に登記を確実に終えられる
相続登記の義務化により、3年以内に登記を済ませなければ過料の対象になります。司法書士に依頼することで、書類不備などを防ぎ、期限内に確実に登記を完了できます。
相続人多数の事例・不動産管理会社との連携
相続人が多数いる場合の具体例と対応策
兄弟姉妹が多い場合:家賃収入をめぐる対立
姫路市内でアパートを所有していた父が亡くなり、相続人は兄弟姉妹5人。毎月の家賃収入が大きいため、
-
「均等に分けたい」
-
「管理してきた人が優先すべきだ」
と意見が対立しました。
対応のポイント
-
司法書士を通じて、法定相続分(民法で定められた取り分)を全員に明示
-
単独で相続する人を決め、その人が他の相続人に代償金(お金での補償)を支払う方法を提示
-
家賃収入や修繕費の試算を示し、現実的な分割案を提案
👉 数字に基づく説明を行うことで、感情的な対立が和らぎ合意に至ることがあります。
相続人の1人が海外在住の場合
賃貸マンションを相続する際、相続人の1人が海外在住で手続きが進まないケースがあります。
対応のポイント
-
在外公館(大使館・領事館)で署名証明書を取得
-
書類のやり取りに時間がかかるため、早めの準備が必須
👉 海外在住者が相続人に含まれると、通常よりも数か月単位で時間が延びる可能性があるため注意が必要です。
認知症の相続人がいる場合
相続人の中に認知症で判断能力が不十分な人がいると、自筆で署名押印しても法的に無効とされる可能性があります。
対応のポイント
-
家庭裁判所に申立てを行い、「成年後見人」を選任
-
後見人が代理人として遺産分割協議に参加
-
後見人の同意を得たうえで相続登記を進める
👉 判断能力に不安がある場合は、早めに家庭裁判所へ相談し、司法書士や弁護士と連携することが重要です。
不動産管理会社との連携
管理会社に任せるメリット
賃貸物件を相続すると、家賃の管理や入居者対応も引き継ぐことになります。管理会社に委託することで、
-
家賃の集金・送金
-
入居者からの修繕依頼や苦情対応
-
空室時の入居者募集
を代行してもらえるため、相続人の負担を大幅に軽減できます。
管理契約の確認・見直し
被相続人がすでに管理会社と契約していた場合、相続人がその契約を引き継ぎます。
-
手数料
-
修繕対応の範囲
-
更新時の対応方法
などを確認し、必要であれば契約を見直すことも可能です。
👉 相続をきっかけに「管理費が高すぎる」「サービス内容が不十分」と気づくケースもあり、契約の棚卸しにも良い機会となります。
相続と賃貸物件を円滑に解決するポイント
-
期限を守ること
相続登記は3年以内。放置すれば過料の対象になるため早めに着手。 -
代表相続人を決めること
相続人多数の場合、代表を決めて家賃や修繕の管理を一本化。 -
専門家を活用すること
-
司法書士:登記手続きや戸籍収集を支援
-
管理会社:賃貸経営を代行
-
税理士:相続税や節税のアドバイス
-
👉 複雑な相続ほど「誰に相談するか」で結果が大きく変わります。
まとめ
賃貸物件の相続は、
-
登記義務化(3年以内)
-
賃貸借契約の継続(家賃や修繕義務も引き継ぐ)
-
相続人多数による管理や収益分配のトラブル
-
姫路エリア特有の空室・老朽化問題
といった課題が重なり、通常の相続よりも手間がかかります。
よくある質問(Q&A)
Q1:相続登記はいつまでに行わなければなりませんか?
2024年4月から相続登記は義務化され、相続が発生したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。過ぎてしまうと10万円以下の過料(行政罰)を受ける可能性があります。
👉 姫路市内の不動産も例外ではありません。遅れるほど必要書類の収集や相続人の調整が難しくなるため、できるだけ早めの着手が安心です。
Q2:賃貸物件を相続した場合、入居者との契約はどうなりますか?
賃貸借契約は自動的に相続人へ引き継がれます。
-
家賃は相続人に支払われる
-
修繕や敷金返還の義務も相続人が負う
👉 入居者に「オーナーが変わったこと」を通知し、家賃の振込先を変更するのが実務上の重要ポイントです。
Q3:相続人が多くて話がまとまらないときはどうすればいい?
相続人多数だと、家賃収入や修繕費の分担をめぐって意見が割れることがあります。
-
代表相続人を選ぶ
-
司法書士に登記手続きを依頼する
-
必要に応じて家庭裁判所の制度(成年後見人、不在者財産管理人など)を利用
👉 感情的な争いを避けるため、法定相続分や不動産・預貯金の資料(課税明細書や残高証明書など)をもとに話し合うのがおすすめです。
Q4:不要な土地や空き家を相続した場合、どうすればいいですか?
2023年から始まった相続土地国庫帰属制度を利用すると、一定の条件を満たす土地を国に引き取ってもらえます。
-
申請手数料:1筆あたり14,000円
-
負担金:管理費10年分相当(立地や面積で変動)
👉 ただし建物付き土地は原則対象外です。老朽化した賃貸物件は、まず解体・更地化を検討する必要があります。
Q5:相続登記の費用はどれくらいかかりますか?
-
登録免許税:固定資産税評価額 × 0.4%
-
書類取得費用:数千円〜数万円(戸籍・評価証明など)
-
司法書士報酬:5万〜20万円程度(案件の複雑さにより変動・各事務所によって異なります)
👉 相続人が多いほど戸籍や印鑑証明の数も増え、実費がかさみやすい点に注意してください。
Q6:姫路市で相続登記をする場合、どこの法務局に行けばいいですか?
相続登記は、神戸地方法務局 姫路支局が管轄です。
-
登記相談は原則予約制
-
オンライン申請にも対応
👉 司法書士に依頼して書類を整え、代理申請してもらうのがスムーズです。「手続きが面倒そうだな」と思ったら司法書士事務所にご相談ください。